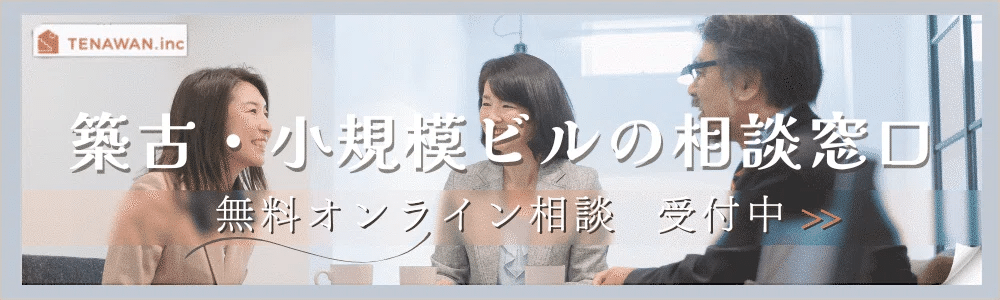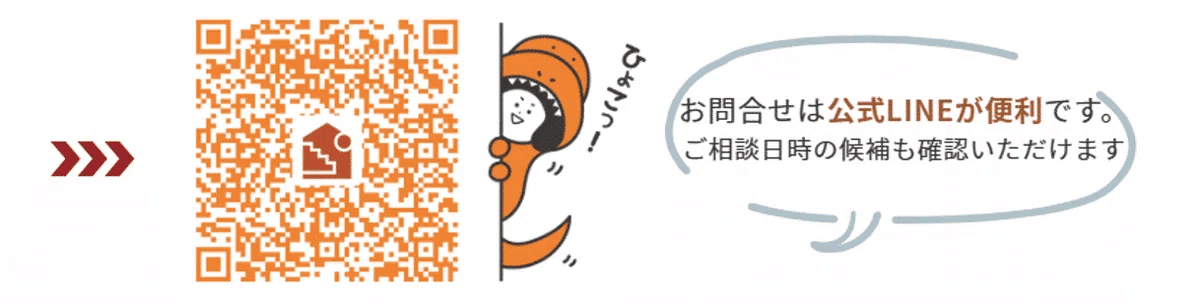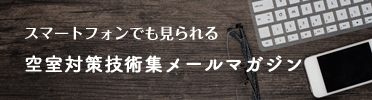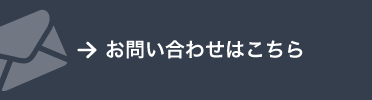ブログ / / 584
PV
築古小規模ビルが生まれ変わる!オフィスリノベーション事例と実践事例
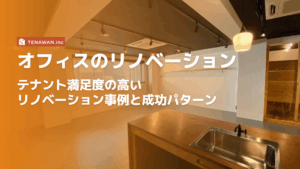
こんにちは。テナワンの石田です。
「近隣に新しいビルが建ち、所有ビルの見劣りが気になる」 「空室がなかなか埋まらず、賃料も下げざるを得ない…」
築30年、40年と歴史を重ねてこられた60~70坪前後のオフィスビルオーナー様から、私たちはこうした切実なご相談を数多くいただきます。先行きの見えない状況に、大きな不安を感じていらっしゃるお気持ち、お察しいたします。
「とはいえ、大規模な改修には多額の投資が必要だし、本当に回収できるかもわからない…」 多くの方が、そう二の足を踏んでいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、ご安心ください。必ずしも、新築同様の大改修だけが正解ではありません。 大切なのは、現代のテナントが本当に求めているニーズを的確に捉え、ビルの個性を活かした「一点突破」の価値を創り出すこと。時にはエントランスや水回りだけといった「ポイントリノベーション」でも、空室の解消、賃料の改善、そして何よりテナント満足度の向上は十分に可能です。
なぜ、私たちにそれができるのか。 それは、テナワン自身も、築古ビルを所有・運営する一人のオーナーだからです。
実際のビル経営で蓄えてきた知見とノウハウを、具体的な事例と共にご紹介します。 あなたのビルに眠る可能性を、ぜひ一緒に見つけ出しましょう。
弊社へのお問合せはコチラからお願いいたします。都内7区を中心に、築古・小規模・様々なビルの様々なご相談に乗らせていただいています。
築古ビルオーナーに知ってほしい、オフィスリノベーションという選択肢
はじめに、オフィスビル再生を考える上で、「リフォーム」と「リノベーション」の違いについて、私たちの考えを整理させてください。これは、自社のオフィスをより良くしたいと考えるベンチャー企業や中小企業の皆様にも、きっと参考にしていただけるはずです。
一般的に、リフォームは汚れた壁紙を張り替えるなど、劣化した部分を「建設当初の状態に近づける」ための修繕を指します。
一方、リノベーションは、現代の働き方に合わせて間取りを変更したり、新たな機能を追加したりすることで、「建物に新しい価値を与え、資産価値そのものを向上させる」ことを目的とした改修です。
特に築年数を重ねたビルが、次々と建つ新しいビルと同じ土俵で戦うには、ただ壊れた箇所を元に戻すだけでは不十分なことが多いです。現代のテナントが持つ価値観や働き方の変化に寄り添い、建物の魅力を根本から引き上げるリノベーションという視点が不可欠になります。
オフィスリノベーションがもたらす具体的なメリットは、主に次の3点に集約されます。
- 空室解消への貢献: 空間が魅力的になることで、借り手が見つかりやすくなります。
- 収益性の改善: 付加価値が向上し、周辺相場に見合った適正な家賃で評価されます。
- 資産価値の向上: 将来的な売却や相続の場面で、有利な条件を引き出す材料となります。
実際に私たちが手掛けた事例の中には、築42年の小規模ビルで、改修前と比べて稼働率が30%向上し、平均賃料も改善したケースがあります。もちろん、これは立地や建物の元々の状態にも左右されますが、的確な投資によって、ビルは着実にその価値を取り戻せると考えています。
小規模ビルには、特有の利点もあります。大規模ビルに比べて改修範囲が限られるため、工期を短縮でき、既存テナント様への影響を最小限に抑えながら価値向上を図れます。
さらに、「小さな会議スペースが一つほしい」「お客様が通る動線だけ綺麗にしたい」「女性用トイレの使い勝手を良くしたい」といった目的に応じた「プチリノベーション」でも、予算を抑えつつ大きな効果が期待できることは、私たち自身が所有する物件で何度も試行錯誤し、実感してきたことです。
ここからはこうした私達の試行錯誤で蓄積してきたオフィスのリノベーション事例を御紹介していきたいと思います。
事例で見るオフィスリノベーション①:コミュニケーションの活性化

リモートワークが普及した今、「なぜ、私たちはわざわざオフィスに来るのか?」という問いが、これまで以上に重要になっています。私はその答えを、単なる「作業の場」としてではなく、仲間と顔を合わせ、予期せぬ会話や出会いから新しい価値を生み出す「交流の拠点」としての役割に見出しています。
しかし、ただ人を同じ場所に集めただけでは、活発なコミュニケーションは生まれません。大切なのは、物理的な壁を取り払うだけでなく、人と人の間に存在する心理的な垣根を越えさせ、「意図しない出会い」や「創造性を刺激する雑談」が自然発生するような仕掛けを、空間に意図的に組み込むことです。
これからご紹介するのは、そうした仕掛けによって、ビル全体の価値を高めることに成功した事例です。これらは、私たち中小ビルオーナーが、今の時代に選ばれるためのヒントに満ちているはずです。
オフィスリノベーション事例:コミュニケーションハブとしてのアイランドキッチン

「オフィスの中心に、あえてキッチンを設ける」 この一つのアイデアが、人の流れとコミュニケーションの質を劇的に変えることがあります。
私たちが担当した五反田のビルでは、ワンフロアの中心にアイランド型のキッチンスペースを設置しました。当初は「オフィスに本格的なキッチンは不要では?」という意見もありましたが、居心地の良いカウンターを設えるなどデザインを工夫することで、今ではそのビルで最も人が集まる「コミュニケーションハブ」として機能しています。
お昼時には「一緒にどうですか?」と自然に声がかかり、誰かがコーヒーを淹れていると、その香りに誘われて部署の垣根を越えた立ち話が始まる。そんな光景が、そこでは日常です。
この「目的がなくても立ち寄れる」という気軽さが、人と人との心理的な距離を縮める触媒になるのです。
計画された会議の緊張感の中では決して生まれない、リラックスした雑談の中からこそ、真のチームワークや革新的なアイデアの芽が育まれるのだと、改めて確信させられた事例です。
オフィスリノベーション事例:「遊び心」が偶発的な交流を誘発する

一見すると業務とは無関係に思える「遊び」の要素。実はこれこそが、創造的な交流を促すための非常に有効なスパイスになり得ます。
かつてGoogleがオフィスにビリヤード台を設置したことは有名ですが、あれは単なる福利厚生という側面だけではありません。「仕事」という共通の目的から解放された場では、普段は接点のない人とも、役職や部署の違いを意識せずに、一個人として対等な会話がしやすくなるからです。
私たちも、管理するビルの屋上でテナントさんたちとビアパーティーを開催することがありますが、仕事の話はそこそこに、趣味や家族の話で盛り上がるうちに、不思議な一体感が生まれます。大掛かりな設備投資は必ずしも必要ありません。
例えば、休憩スペースにボードゲームを数種類置いておくだけでもいいでしょう。誰かがそれを手に取れば、自然と人が集まり、会話が始まる。そうした「仕事と遊びの境界が曖昧な時間」にこそ、次の大きなアイデアの種は眠っているのではないでしょうか。
オフィスリノベーション事例:地域との交流が、新たな価値観を生む

ビルの価値は、その建物の中だけで完結するものではありません。ビルがその「まち」の一部であることを意識し、地域に開かれた存在になることで、新たな価値が生まれます。
私たちが運営していたビルの一つでは、「まちの公園のような場所にしよう」というコンセプトを掲げ、近隣の方々にコーヒーを無料で提供したり、地域のお祭りにテナントさんと一緒にヨーヨー釣りの屋台を出店したりした経験があります。
テナントの社員さんたちが、普段の業務では決して出会わない地域の方々やお子さんたちと触れ合う。こうした体験は、新鮮な刺激やリフレッシュの機会になるだけでなく、テナントさん同士が共同で何かを運営することで、仕事上の顔とは違う一面を知り、関係性を深める絶好の機会になったと、大変ご好評をいただきました。
リノベーションというと、つい内装や設備といった「ハード」の改修に目が行きがちですが、こうしたイベントのような「ソフト」の仕掛けもまた、テナントの満足度を育み、長く愛されるビルを創るための重要な要素なのだと、私たちは考えています。
事例で見るリノベーション②:多様化する「会議」のニーズに応える
働き方の変化は、「会議」そのものの概念をも大きく変えつつあります。かつて主流だった、関係者全員が大きな会議室に集まり、何時間もかけて議論するような重厚長大な会議は影を潜め、現代では、2〜3人での短時間の打ち合わせや、遠隔地の相手と繋がるオンラインでの情報共有が、ビジネスの速度を左右する重要な要素となっています。
私たちビルオーナーも、こうしたテナント側の働き方の実態に目を向け、柔軟な場を提供していくことが、ビルの価値を高め、長く選ばれ続けるために不可欠です。
とはいえ、私たちのような中小規模のビルで、立派な会議室をいくつも確保するのは、スペース的にもコスト的にも現実的ではありません。そこで重要になるのが、かしこまった「会議室」という発想から一歩進んで、予約なしでも気軽に使える「対話のスペース」をいかに創り出すか、という視点です。
ここでは、多様化する現代の「会議」の形に寄り添い、テナントの生産性向上に貢献するためのリノベーション事例をご紹介します。
、
オフィスリノベーション事例:ビル1階を、誰もが集えるカフェ空間に

ビルの1階、それは建物の「顔」とも言える場所です。この場所を、単なる無機質なエントランスホールではなく、テナントや地域の人々が誰でも利用できるカフェ空間として再生させる。これは、ビル全体の価値観を根底から変える力を持つ、非常にパワフルなアイデアです。
カフェがビルの「顔」となることで、街に対して開かれた、ウェルカムな雰囲気が生まれます。
さらに、「入居テナントはコーヒー1杯無料」「テナント主催のイベントでの利用を歓迎する」といった仕組みを加えれば、そこはテナント同士が自然に集う交流拠点へと進化します。仕事場としてだけでなく、有益な情報交換や新たな出会いが生まれるコミュニティとして機能し始めるのです。
その結果、たとえ空室が出たとしても、不動産会社に頼る前に、既存テナントからの紹介や口コミですぐに次の入居者が決まってしまう。
そんな「自走する魅力」を持った強いビルへと成長していきます。
オフィスリノベーション事例:共用部に設ける、どのテナントも使える会議専用スペース

リモートワークの浸透により、オンライン会議はすっかりビジネスの日常風景となりました。しかし、多くのテナントが「Web会議の場所がない」という切実な悩みを抱えています。
自席で参加すれば、周囲の雑音が気になったり、逆に自分の声が同僚の集中を妨げていないかと、余計な気を遣ったりするものです。
この普遍的な課題に対し、私たちが積極的に提案しているのが、共用廊下の片隅などを利用した、1〜2人用の電話ブースや、WEB会議専用の小さな個室を設置するリノベーションです。
これは、比較的小規模な工事で、低コストで導入できるにもかかわらず、テナントの日々の業務効率と満足度を劇的に向上させます。周りを気にすることなく会議に集中できる環境は、テナントの生産性に直接貢献します。
こうした細やかな配慮は、単なる設備投資以上の意味を持ちます。「このビルのオーナーは、私たちの働き方を本当に理解してくれている」。そのように感じていただけることが、強い信頼関係を育み、築古ビルがテナントから積極的に選ばれる、確かな理由になるのです。
もちろん、こうした改修には初期投資が伴います。しかし、私たちテナワンでは、オーナー様とリスクを分かち合い、共に価値を創造していく、というパートナーシップの形も常に模索しています。大切なのは、最初の一歩をどう踏み出すか。ビルの未来について、一緒に頭を悩ませることから始めてみませんか。
弊社ではビルを「ビルの空室を借上げ、オーナー様の費用負担ゼロで改修」というサービスを提供させていただいています。もしご興味いただけるようでしたら気軽にお問合せください。
事例で見るリノベーション③:テナントの社員満足度を高める
これからの時代、企業が優秀な人材を惹きつけ、長く活躍してもらうためには、給与や待遇といった条件面だけではなくなってきています。社員が日々多くの時間を過ごすオフィスが、「いかに心身ともに健やかで、自分らしくいられる場所か」という点が、極めて重要な経営課題になっています。
ある先進的な企業の経営者が「魅力的なオフィスへの投資は、求人広告費よりもよっぽど効果的な採用戦略だ」と話してくれたことがありますが、私も全く同感です 。ビルオーナーが提供する空間の質が、入居テナントの採用力、ひいては企業の持続的な成長を左右する時代なのです。
ただ綺麗なだけのオフィスではなく、「ここで働く自分が好きだ」と社員に感じてもらえる場所を提供できるか。
その視点から、テナントに長く愛されるためのリノベーション事例をご紹介します。
オフィスリノベーション事例:自転車通勤者のための「土間」スペース

健康志向や環境意識の高まりから、自転車で通勤するワーカーが増えています。しかし、多くのオフィスビルでは駐輪場の確保が難しく、屋外で雨ざらし、というケースがほとんどです。高価なロードバイクを通勤で使う方にとって、盗難のリスクは常に付きまといます。
そこで、私たちがとあるビルのリノベーションで試みたのが、エントランスを入ってすぐのデッドスペースを、思い切ってコンクリート打ちっぱなしの「土間」にしてしまうことでした 。
ここなら、愛車を安心して室内で保管できますし、雨で濡れたヘルメットやウェアを気兼ねなく乾かすこともできます。
自転車を置くだけでなく、大きな荷物の一時保管や、少し汚れる可能性のある軽作業の場としても活用できる、多目的なユーティリティスペースです。
エントランスにこうした空間があることは、テナントにとって嬉しい驚きであり、他の画一的なビルにはない、気の利いた付加価値となります。大規模な工事ではなく、少しの発想の転換で、テナントの日々の満足度を大きく向上させることができた好例です。
オフィスリノベーション事例:「屋上」という未開拓の資産で、心と体を整える

ほとんどのビルで活用されていない屋上。私たち中小ビルオーナーにとって、ここはまさに「眠っている宝の山」です 。ウッドデッキを敷いて休憩スペースにするだけでも十分に魅力的ですが、もう一歩踏み込んで、テナントのウェルネス(心身の健康)に貢献する場として活用してみてはいかがでしょうか。
例えば、週に一度、プロのインストラクターを招き、屋上でヨガレッスンを開催する。最近はオンラインで簡単に出張サービスを予約でき、気軽に企画することが可能です。
ビルという日常の中に、空の下で深く呼吸し、体を動かす非日常の時間が生まれる。この体験は、社員の心身のリフレッシュはもちろん、仕事の生産性や創造性を高める上でも、計り知れない効果をもたらします。
テナントの内覧の際に屋上を見てもらうと、その風通しのよさや気持ちのよさに「リフレッシュがしやすいです」や「屋上でヨガイベントを開催したこともあるんですよ」とお伝えすると、多くのテナントさんに好感を持っていただけます。
特に最近の会社はオフィスのデスクワークが増えや腰や背中・肩に負担を抱えている方も多いです。
その疲れを精神的にも肉体的にもほぐすことができるイメージを持っていただけると様々なビルのなかで「このビルが良い」と選んでいただける理由になります。
ただし、屋上があるから開放すればいい!という話ではなく、安全面はもちろんのこと水はけやイベント利用時の運営等、使いやすい設備に変えたうえで利用ルール等をきちんと定めてあげることも重要です。
オフィスリノベーション事例:テナントによる自由な内装カスタマイズを許容する

多くの中小ビルでは、賃貸借契約における「原状回復義務」が、いわば常識となっています。しかし、私たちはあえて、その“常識”を疑ってみました。
「事前に計画を共有・承諾した範囲であれば、テナントが自由に内装を改装しても構いません。そして、その部分の原状回復は不要です」という、新しいルールの提案です 。
この試みは、特にクリエイティブ系のテナントから、とてもご好評いただくことができました。彼らはオフィスを単なる作業場所ではなく、自社のブランドイメージや働き方を体現する「表現の場」でもあるからです。
壁の色を塗り替え、自分たちの手で棚を造作し、愛着のある空間を創り上げていく。そのプロセス自体が、仕事へのモチベーションや組織の一体感を飛躍的に高めるのです。
オーナー側の視点に立てば、これは内装の初期投資を抑えつつ、テナントのクリエイティビティと費用負担によって、ビルの価値が自然と向上していく、Win-Winになれる非常に合理的な戦略とも言えます。
事例で見るオフィスリノベーション④:新たなアイデアの創発を促す

オフィスは、決められた業務をこなすだけの場所ではありません。多様な知識や才能が出会い、**「新たなアイデアを生み出すためのプラットフォーム」**としての役割が、今まさに求められています。
優れたひらめきというものは、静まり返った部屋で一人、腕を組んでいても、なかなか天から降ってはきません。むしろ、多様な情報や人々との予期せぬ化学反応、心地よい喧騒の中にこそ、そのヒントは隠されているのではないでしょうか。
これからのオフィスに必要なのは、その**「創造的な偶然」**を誘発し、アイデアという無形の資産が自由に生まれ、発信されるための仕掛けです。ここでは、テナントの知的生産性を最大化し、新たな価値創造の拠点となるためのリノベーション事例をご紹介します。
オフィスリノベーション事例:壁一面を「思考のキャンバス」に変える
素晴らしいアイデアは、往々にして、会議室での雑談や何気ない会話の最中に、予期せず生まれます。その貴重な瞬間を逃さず、誰もがすぐに書き留め、発展させられる場所があったら、どうでしょう。
そこで私たちが提案し、非常に好評をいただいているのが、会議室の壁一面をまるごとホワイトボード化するリノベーションです。
議論が白熱し、アイデアが次々と生まれる。その思考の発散を、ボードのサイズが妨げることはありません。常に全体像が目の前にあることで、「その意見、面白いね」「こんな視点も加えられないか?」と、参加者全員でアイデアを磨き上げることができます。
壁一枚が、チームのクリエイティビティを解放する巨大なキャンバスになる。これは、組織の集合知を育むための、極めてシンプルかつ効果的な仕掛けだと考えています。
オフィスリノベーション事例:小規模ビルだからこそ可能な「オフィスシェア」という選択

中小規模のビルだからこそ、アイデア創発のために打てる有効な一手があります。それが、「複数の会社でオフィスをシェアする」という選択肢を、オーナー側が積極的に後押しすることです。
私自身、起業したての頃は、不動産業界の先輩のオフィスに間借りさせてもらい、仕事の相談に乗ってもらうなど、公私にわたり大変お世話になりました 。
例えば、設計事務所とWebデザイナー、弁護士と司法書士など、業務上の親和性が高いテナントが同じ空間で働くことで、そこには自然な協業やアライアンスが生まれる土壌ができます 。自分たちの専門外の課題に直面した時も、隣の席のプロフェッショナルに気軽に相談できる。そうした環境そのものが、新たなビジネスチャンスやイノベーションの源泉となるのです。
もちろん、そのためにはオーナー側が、同居を正式に認める契約書のひな形を用意したり 、入居者同士の交流会を企画したり と、その関係性を育むためのサポートをすることも大切です。
それは、ビルオーナーが単なる「家主」から、新たな価値を生み出す「コミュニティ・ファシリテーター」へと進化する、ということでもありますし、私達が支援させていただいている物件では私達テナワンが間に入ってオーナー様とテナント様が交流するイベントやルールを企画・運営させていただいています。
低予算で大きな効果を狙う、小規模オフィスビル向けのリノベーション再生術
ここからは、限られた予算の中でも実現可能な、費用対効果の高い改修手法について、より具体的にご紹介します。
低予算リノベーションのリアルな成功事例(築30年・40坪オフィスビル)
私たちが以前に手掛けた、とあるビルでのプロジェクトです。総工費280万円という予算の中で、以下の改修を行いました。
まず、建物の第一印象を左右するエントランスです。壁面を明るい色の塗装で仕上げ直し、照明を省エネで明るいLEDへと交換。そして、古びた床タイルは、既存のタイルの上から新しいものを重ねて貼る「重ね貼り工法」を採用しました。これにより、解体費用と工期を大幅に圧縮しながら、見た目を劇的に改善することに成功しました。
各階の廊下は、壁紙を全面的に張り替えると共に、一部にアクセントクロスを用いることで、単調だった空間にリズムと個性を与えました。トイレについては、便器などの衛生陶器の交換は見送り、クロスと床材の張り替えに集中することで、清潔感を飛躍的に向上させています。
そして、このプロジェクトで最も効果的だったのが、ビル名称の変更と新しいロゴサインの設置です。「○○第2ビル」という、どこにでもありそうな無機質な名称から、周辺の歴史や地名の響きを活かした、親しみやすく記憶に残りやすい名前に変更しました。新しいロゴをまとったサインが設置された瞬間、ビルの外観の印象は一新され、新しい物語が始まったことを強く印象付けました。
オフィスビルのエリア別・リノベーションの優先順位と期待できる効果

限られた予算を有効に使うためには、どこから手をつけるか、改修の優先順位を見極める戦略的な視点が不可欠です。私たちの経験上、以下の順番で投資対効果が高いと考えています。
- エントランス周り 内見者が最初に足を踏み入れ、そのビルの印象を決定づける最重要エリアです。比較的少ない投資で、最も大きな効果が期待できます。照明を明るくし、清潔感を保つだけでも、テナント候補者の心証は大きく変わります。
- お手洗い(特に女性用) 今や女性も企業の主戦力として活躍し、オフィス選びにおいても女性社員の意見が重視される時代です。特に女性用のトイレ空間の清潔感や快適性は、成約率に直接影響するといっても過言ではありません。全面的な改修が難しい場合でも、大きな鏡や明るい照明に交換するだけでも、印象は格段に良くなります。
- 各階の廊下・共用部 毎日、誰もが利用する空間です。この場所の快適性を高めることは、既存テナントの満足度向上と、新規テナントの内見時の印象アップ、その両方に効果を発揮します。
小規模ビルの改修で失敗しないための3つのポイント
低予算での改修を成功に導くためには、いくつか注意すべき点があります。
- 法的な制約を事前に確認する:改修内容によっては、建築基準法上の手続きや届け出が必要になる場合があります。計画段階で専門家に確認し、法的な問題をクリアにしておくことが重要です。
- 原状回復の範囲を明確にしておく:賃貸物件の場合、将来テナントが退去する際の原状回復費用も念頭に置いた改修計画が求められます。
- 工事期間中のテナントへの配慮を忘れない:既存テナントへの影響を最小限に抑える工程計画が、プロジェクトを円滑に進める鍵です。特に小規模ビルの場合、工事中の騒音や通行制限がテナントの業務に直接的な影響を与えやすいため、事前の十分な説明と、可能な限り短期間で完了する緻密な工事計画が不可欠です。
今すぐ始められる、築古ビル再生の第一歩
ここまで様々な事例や手法をご紹介してきましたが、「理屈は分かったが、具体的に何から手をつければいいのか…」と感じていらっしゃる方も多いかもしれません。最後に、小規模ビルのリノベーションを成功へと導くための、具体的な思考のステップをお伝えします。
小規模オフィスビルのリノベーションにおける成功要因
私たちの経験から、成功する再生プロジェクトには、いくつかの共通点があります。
まず、未来のシナリオに基づいた、明確な目標設定です。「なんとなく古くなったから直したい」という漠然とした動機でも最初はいいのですが、実際に投資する際には「2年以内に稼働率を80%以上にする」「平均賃料を周辺相場並み(●●万円)に設定する」といった、具体的な数値目標を掲げることが重要です。
そして、その目標設定には、いつ、誰が、どのように相続するのか、将来的な建て替えの時期は決まっているのか、金利や資材価格の今後のトレンドはどうか、といった複数の時間軸の要素を加味する必要があります。様々なシナリオを想定し、その中で最も成功確率の高い目標を定め、そこから逆算して適切な投資予算を導き出すのです。
小規模オフィスビルのリノベーション計画立案・5つのステップ
ステップ1:信頼できるパートナーを探す ここが一番大事だと思っているのですが、金利や資材価格等の外部環境から自社ビルの状況、更には将来設計も含めて成功確率の高いシナリオを客観的に相談できるパートナーは大切です。御自身でシナリオを作れる場合でも外部の第三者の目線で見て「違和感はないのか?」「大きなリスクを取りすぎていないか」といった検証は大切です。
ステップ2:現状分析と目標設定 次に建物の現在の稼働状況、賃料水準、周辺の競合物件などを徹底的に調査し、自らのビルの「現在地」を客観的に把握します。その上で、改修後に達成したい稼働率や賃料水準といった目標を、具体的な数値で設定します。
ステップ3:改修範囲と予算の検討 設定した目標を達成するために、どこまでの改修が必要かを検討し、概算の予算を算出します。この時、複数のプランを用意し、それぞれの投資回収期間をシミュレーションすることをお勧めします。目的が明確であれば、本記事でご紹介したような「プチリノベーション」でも、十分に効果を発揮できる可能性があります。
ステップ4:詳細設計と工程計画 リノベーションの骨子が固まったら、詳細な設計図を作成し、具体的な工程計画を立てます。既存テナントへの影響を最小限に抑える工程を組むことが、円滑な工事の鍵となります。
ステップ5:施工管理と効果測定 工事が始まったら、計画通りに進んでいるか品質管理を徹底します。そして、完了後は、ステップ1で設定した目標に対して、どのような効果があったかを具体的に測定します。もし期待した効果が得られない場合は、その原因を分析し、追加の対策を検討する柔軟性も必要です。
ここまで様々な手法やステップをご紹介しましたが、これらはあくまで地図の一部です。
実際には、ビル一棟一棟の個性や、オーナー様お一人おひとりの未来図によって全く異なるものになります。私たちテナワンは、時にオーナー様とリスクを分かち合うパートナーとして、その航海に「伴走」することもあります。
築古ビルも、適切な再生手法を施すことで、まだまだ長期間にわたり収益を生み出す、価値ある資産として輝き続けることができます。建て替えという大きな決断の前に、まずはリノベーションという選択肢から、皆さんのビルにどのような可能性があるのか、様々な観点からお話ができたら幸いです。
- タグ
-