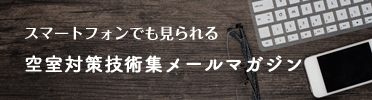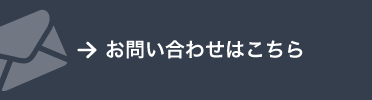ブログ / / 939
PV
老朽化ビルの未来と再生|最終手段の建て替えと収益改善をさせる新しいアイディア

こんにちは。テナワンの石田です。
「うちのビルも、もう古いから…」
築30年、40年と歴史を重ねたご自身のビルを前に、そう呟いた経験のあるオーナー様は、決して少なくないのではないでしょうか。空室がなかなか埋まらず、やっと入ってくれたテナントさんからは設備のクレーム。毎年かさんでいく修繕費に頭を悩ませ、将来への漠然とした不安を感じている…。
そのお気持ち、私も自社で経営するビルオーナーの一人として痛いほどよく分かります。
しかし、その「老朽化」という一言で、ご自身のビルが持つ無限の可能性に蓋をしてしまうのは、本当にもったいないことです。結論から言えば、適切な対策を講じれば、老朽化ビルは新築ビルにも負けない収益性と資産価値を持つ「稼げるビル」へと生まれ変わらせることができます。
この記事では、老朽化ビルが抱える本当のリスクとは何かを直視し、巷で言われる「建て替え」という選択肢がなぜ最終手段なのか、そして、あなたのビルを再生させるための具体的な選択肢と費用対効果について、数々のビルを再生させてきた私の経験と知見を全てお話ししたいと思います。
放置すれば資産価値ゼロも?老朽化ビルが直面する4大経営リスク

まず、目をそらさずに現状を把握することから始めましょう。老朽化したビルを放置した場合、どのようなリスクが待ち受けているのか。
これは、単に「古くなる」という話ではありません。経営そのものを揺るがしかねない、4つの深刻なリスクが存在します。
老朽化ビルのリスク1.空室率の上昇と賃料下落の「負のスパイラル」
これが最も分かりやすいリスクですよね。建物や設備が古くなると、テナントにとっての魅力が薄れ、空室が増え始めます。
そもそも入居オフィスをテナントさんが探すときネット仲介会社のサイトで「築年数」を指定します。その範囲から外れてしまうと表示もされません。
さらに空室を埋めようと賃料を下げると、今度はビルの収益性が悪化し、必要な修繕に回すお金がなくなります。その結果、ビルはさらに老朽化し、ますますテナントから敬遠される…まさに、抜け出すことの困難な「負のスパイラル」です。仲介サイトなどでオフィス探しをしているお客さんからすると、いろんな候補物件が表示されるので、「どうせなら新しい方がいいよね」という選択をされる傾向が強いです。
老朽化ビルのリスク2. 雪だるま式に増える「維持管理費」という時限爆弾
建物も人間と同じで、歳をとればとるほど、メンテナンスにお金がかかります。特に築30年を超えると、外壁、屋上防水、給排水、空調といった主要な設備が一斉に寿命を迎え、大規模な更新が必要になります。
ビューローベリタスの調査によれば、築30年以上のビルの年間維持管理費は、新築時の約2.5倍に達するケースも珍しくありません 。計画的な修繕を怠っていると、ある日突然、数千万円単位の「想定外の出費」に見舞われる。これは、ビル経営における非常に恐ろしい時限爆弾なんです。
老朽化ビルのリスク3. テナントも従業員も離れる「耐震性」への不安
1981年以前の「旧耐震基準」で建てられたビルは、特にこの問題が深刻です。
今や、企業がオフィスを選ぶ際、従業員の安全確保は最優先事項。BCP(事業継続計画)の観点からも、現況の耐震基準を満たしていないビルに対しては不安視する人がいたり、特に上場企業はコンプライアンス的に検討候補から外さざるを得ないことがあります。優良なテナントほど、この傾向は強いと言えるでしょう。「万が一」の事態に備えるのは、ビルオーナーとしての最低限の責任であり、これを怠ることは、テナントからの信頼を失うことに直結します。
老朽化ビルのリスク4. 意思決定を阻む「相続・権利関係」の壁
これは、特に先代からビルを受け継いだオーナー様が直面しやすい、非常に根深い問題です。相続によってビルが兄弟や親戚との共有名義になっていると、いざ大規模な修繕や建て替えをしようにも、共有者全員の合意形成が非常に難しくなります。「私はお金を出したくない」「売却した方がいい」など、意見がまとまらずに時間だけが過ぎていき、その間にもビルは価値を失い続ける…というケースは、後を絶ちません 。
その対策、間違っていませんか?老朽化ビル再生の前に知るべき「本当の問題点」

さて、これらのリスクを前にして、「やはり古いのが問題なんだから、建て替えるか、大規模修繕するしかない」と考えるのは、少し早計かもしれません。私が多くの現場で見てきたのは、問題の本当の根っこは、建物の物理的な古さ“だけ”ではない、ということです。
機能で劣っても「感情価値」で勝負する時代へ
考えてみてください。今の時代、私たちはスマートフォンを選ぶとき、スペック表の数字だけで決めるでしょうか? デザインの美しさ、操作感の心地よさ、持っていることの満足感…そういった「感情」に訴えかける価値が、購買の大きな決め手になっていますよね。
オフィス選びも、全く同じです。
立地、広さ、賃料といったスペックだけで比較される時代は、もう終わりつつあります。テナントさんが本当に求めているのは、「そこで働く時間が、いかに快適で、創造的で、誇らしいものになるか」という体験価値、つまり「感情価値」なのです。
「カッコいいオフィス」は、最高の求人広告になる
「採用のためにオフィスを改装した」という経営者の話は、今や珍しくありません。優秀な人材ほど、自分が働く環境の「質」に敏感です。
古くて暗いオフィスは、「この会社は社員に投資しない会社だ」という無言のメッセージになりかねません。逆に、古くてもセンス良くリノベーションされたオフィスは、「この会社はクリエイティブで、働く人を大切にしている」という強力なブランディングツールになるのです。
「どこも同じ」から抜け出す、「個性」という武器
白い壁、グレーのタイルカーペット、無機質な蛍光灯…。そんな没個性的なオフィスに、愛着を持つことは難しいかもしれません。
老朽化ビルは、その歴史そのものが「個性」です。あえてコンクリートの躯体を見せる、天井を抜いて開放感を出す、レトロな照明を活かす…。
新築ビルには出せない「味」や「物語」を武器にすることで、「ありきたりのオフィスは嫌だ」という感度の高いテナントを惹きつけることが可能になります。
募集方法と管理体制は、時代遅れになっていないか?
もう一つの重要な視点が、「運営」の問題です。いくらリノベーションで魅力的な空間を作っても、その価値が届くべき人に届かなければ意味がありません。
昔からの付き合いで、地元の不動産屋さんに募集を任せきりにしていないでしょうか? その会社は、今のテナントさんが当たり前のように使っている物件検索サイトやSNSを駆使して、あなたのビルの魅力を発信してくれているでしょうか。
周辺の相場をきちんと分析し、あなたのビルの「感情価値」を価格に反映させた、戦略的な賃料設定はできているでしょうか。
「建物が古いから客付けが悪い」のではなく、「客付けの方法が古いから客付けが悪い」。多くの場合、原因はこちらにあるのです。ハード(建物)の対策を考える前に、まずはソフト(管理・募集)の体制を見直すだけで、状況が劇的に改善するケースは少なくありません。
費用対効果で考える老朽化ビルの再生オプション3選
では、いよいよ具体的な建物の対策について考えていきましょう。オーナー様の予算やビルの状況に応じて、選択肢は一つではありません。ここでは代表的な3つの選択肢を、費用対効果の視点から比較してみます。
選択肢① 大規模修繕:守りの投資と限界(費用:数千万円)
外壁塗装や屋上防水、設備の更新など、建物の基本的な性能を維持するための「守りの投資」です。これは、ビルの健康を保つために必須ですが、あくまでマイナスをゼロに戻す行為。これだけで競争力が劇的に上がるわけではない、と認識しておくことが重要です。
選択肢② リノベーション:攻めの投資で価値創造(費用:修繕費+α)
「感情価値」や「個性」を生み出すための「攻めの投資」です。例えば、使われていなかった屋上をウッドデッキのテラスにしたり、暗いエントランスをホテルのラウンジのような空間に変えたり。もちろん専用室内をデザイン性の高いものに改修することももちろん重要です。費用は修繕費にプラスαでかかりますが、周辺相場より高い賃料での成約や、空室期間の大幅な短縮が期待でき、費用対効果は非常に高いと言えます。どこに投資すればテナントの心に最も響くか、その見極めが成功の鍵です。
選択肢③ リファイニング建築:デザインリノベーション + 耐震補強(費用:新築の約1/4~1/3)
「建て替え」を選択する前に、既存の建物を活かしながら安全性とデザイン性を両立させる、最も費用対効果の高い手法がこちらです。
選択肢②でご紹介した「攻めのリノベーション」に、必要な耐震補強を組み合わせることで、ビルの収益性と安全性を同時に高めます。最大のメリットは、建て替えに比べて工期が短く、解体工事も不要なため、テナントの退去費用や数年にわたる家賃収入の逸失リスクを大幅に軽減できる点です。
ビルの状態や求めるグレードにもよりますが、新築の1/4~1/3という費用感で実現できるケースも少なくありません。築50年のビルでも、適切な耐震補強(坪5〜15万円程度)とポイントを絞ったリノベーションにより、建て替えずとも競争力のあるビルへと再生させることは十分に可能です。
【コラム】「建て替え」が最終手段である理由
築年数が経つと銀行などから提案されることの多い「建て替え」ですが、私はこれは“最終手段”、または十分にシュミレーションした後の合理的な意思決定でするべき判断だと考えています。なぜなら、①数億円という莫大な費用、②解体から完成までの約2年間に及ぶ無収入期間(更に最近は建築費高騰に伴う工期の長期化もあります)、③現行法規によって建物規模が縮小してしまうリスク、という3つの大きなハードルがあるからです。特に中小規模のビルオーナー様にとっては、経営の根幹を揺るしかねない大きなリスクのある判断だと思います。
実践!老朽化ビル再生プロジェクトの進め方
では、具体的に何から始めればいいのか。複雑に見える再生プロジェクトも、手順を踏めば必ず道は拓けます。
ステップ1:信頼できる「パートナー」を見つける
なによりもオーナー様のビジョンに共感し、同じ船に乗って汗を流してくれる、信頼できるパートナー(設計事務所やコンサルタント)を見つけることが、プロジェクトの成否を分けます。単に言われたことをやる業者ではなく、オーナー様以上にそのビルの可能性を信じ、ユニークなアイデアを提案してくれる相手が理想です。
ステップ2:新しい付加価値を付けた新しいビルの収支シュミレーションを立ててもらう
次に、信頼できる「パートナー」に“付加価値を付けた新しいビルの収支シュミレーションを立ててもらう”ことが大切です。そのシナリオも金利の変動や将来的な家族構成等、いくつかの前提条件に分けて検討することが大切だと考えています。ここまでやると「どれぐらい投資する」ことが、そのビルにとって“合理的と考えられるか”や“どこまでのリスクなら取れるか”を具体的に検討できるようになります。
ステップ3:事業計画と資金調達(補助金・助成金の活用)
最後に、こうした具体的なシュミレーションとリスクを検討したうえでパートナーと共に、複数の再生シナリオに基づいたリアルな事業計画を立てます。その計画書を持って金融機関と交渉し、資金調達の道筋をつけます。この際、耐震改修や省エネ化に対する国や自治体の補助金・助成金制度は、必ずチェックしましょう。活用できれば、自己資金の負担を大幅に軽減できます。
まとめ:老朽化ビルは「お荷物」ではなく、未来を創る「原石」である
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
老朽化ビルは、確かに多くの課題を抱えています。しかし、それは決して「お荷物」ではありません。オーナー様自身の想いと、ほんの少しの勇気、そして信頼できるパートナーとの出会いがあれば、他のどんなビルにも負けない魅力と価値を秘めた「輝ける原石」なのです。
「古いから、もうダメだ」と諦める前に、ぜひ一度、ご自身のビルが持つ可能性を信じて、その声に耳を傾けてみてください。そして、そのビルをどんな未来に導きたいか、ワクワクしながら想像してみてください。
私たちテナワンは、そんなオーナー様の情熱に火をつけ、その想いを形にするお手伝いをしたいと、心から願っています。あなたのビル再生の物語、ぜひ一緒に始めさせてください。
- タグ
-