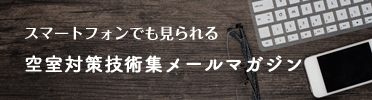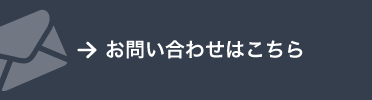新着情報 / / 551
PV
【不動産会社こぼれ話】高齢入居者と向き合うということ

こんにちは、テナワンの小林です。
今回は普段と趣向を変えて、ビルの賃貸管理の仕事をやっている中でとても印象に残ったエピソードを書きたいと思います。
今回ご紹介するのは、長年にわたりテナントとして入居していたあるクリニックとの契約終了までの出来事です。

■ 院長が突然、病に倒れる
そのクリニックの院長は、長年にわたり同じ場所で診療を続けてこられた高齢の先生でした。長期入居ということもあり、貸主としても安心してお任せしていたのですが、ある時期から賃料の振込が途絶えます。
不思議に思って確認したところ、院長が病気で急きょ入院されていたことが分かりました。一人暮らしで身の回りのことはすべてご自身でされていたため、入院中は銀行にも行けず、賃料の支払いが困難な状況だったのです。
■ 滞納と退去、でも進められない現実
その後も賃料の滞納は続き、こちらとしては解約の手続きをお願いせざるを得ない状況となりました。ですが、院長は退院の見込みが立たず、「自分以外には手続きを頼める人がいない」とのことで、解約の手続きがなかなか進みません。
それでも入院先との郵便のやり取りと体調がいい時につながる電話で、かろうじて解約通知書だけは出してもらいました。問題はその後です。クリニックの内部には、診療機器やカルテ、医薬品など多くの設備が残されており、これらの撤去や原状回復にかかる費用は高額です。滞納分の賃料と合わせると、預かっている敷金をはるかに上回る見込みでした。
■ 連帯保証人への請求は「しない」という選択
残置物処分と原状回復工事の見積書を見た院長からは、とても支払える金額ではないとのこと。敷金で足りない分は、通常なら連帯保証人に請求することになります。契約書の連帯保証人欄に記載されている住所を訪ねてみましたが、表札はなく、住んでいるかどうかも確認できません。
この件を院長に伝えると、「連帯保証人の弟とはもう長らく連絡を取っていない。勘弁してほしい。」と懇願されました。貸主は最終的に「今回は連帯保証人への請求は行わない」と判断し、預かっている敷金以外に請求することを断念しました。
■ 「もう長くないんだよ」と語った院長の想い
残された課題は、残置物の撤去と明け渡しの意思を明確にする「覚書」への同意です。カルテや医薬品など、こちらで処分できないものは院長が一時帰宅した際に処理してもらいました。
その時、人工呼吸器のチューブをつけた院長が力なく笑いながら言った一言が忘れられません。
「もう長くないんだよ」
私たちは業務として動いていますが、このような瞬間にふと心が揺れます。
その後、覚書の内容を院長に電話でご説明し、ようやく合意を得ることができました。覚書は入院先の病室宛てに郵送しましたが、1週間経っても返送されません。病院に連絡しても、親族でなければ病状は教えられず、「もうその病室にはいない」という一言だけが返ってきました。
もしかすると、自宅に戻られたのかもしれない——。私たちは最後の確認として、院長の自宅を訪ねましたが応答はなく、院長に連絡を取る手段は完全に無くなりました。
それから数週間後、院長のご家族という方から電話がありました。院長は、電話で覚書のやり取りをしたその数日後に息を引き取ったとのこと。葬儀などが終わり、スマートフォンの解除がやっとできて着信を見たところ、こちらから何度か入れていた留守電を聞いて連絡をくれました。郵送した覚書はご家族の方が返送してくれて、この手続きにピリオドを打つことができました。
■ 管理業務を超えて、「人」と向き合う
賃貸借契約は法と契約で結ばれた「事務的な関係」のように見えます。しかし現場では、その契約の裏に「人の人生」が存在しています。
今回のケースでは、滞納や残置物の処分、連帯保証の問題など、管理者として解決すべき多くの課題がありました。多くを経験してきた上席からは、借主がどんなに気の毒であっても、心を鬼にして手続きをするしかない時があると言われていました。それでも最後まで「借主がどのようにこの空間と別れを告げるか」に寄り添いたいという思いがありました。
高齢化が進む中、このような事例はこれからも増えるでしょう。私たち不動産の管理に関わる者として、契約だけでは測れない「人との関係」に、どこまで向き合えるかが問われているのかもしれません。